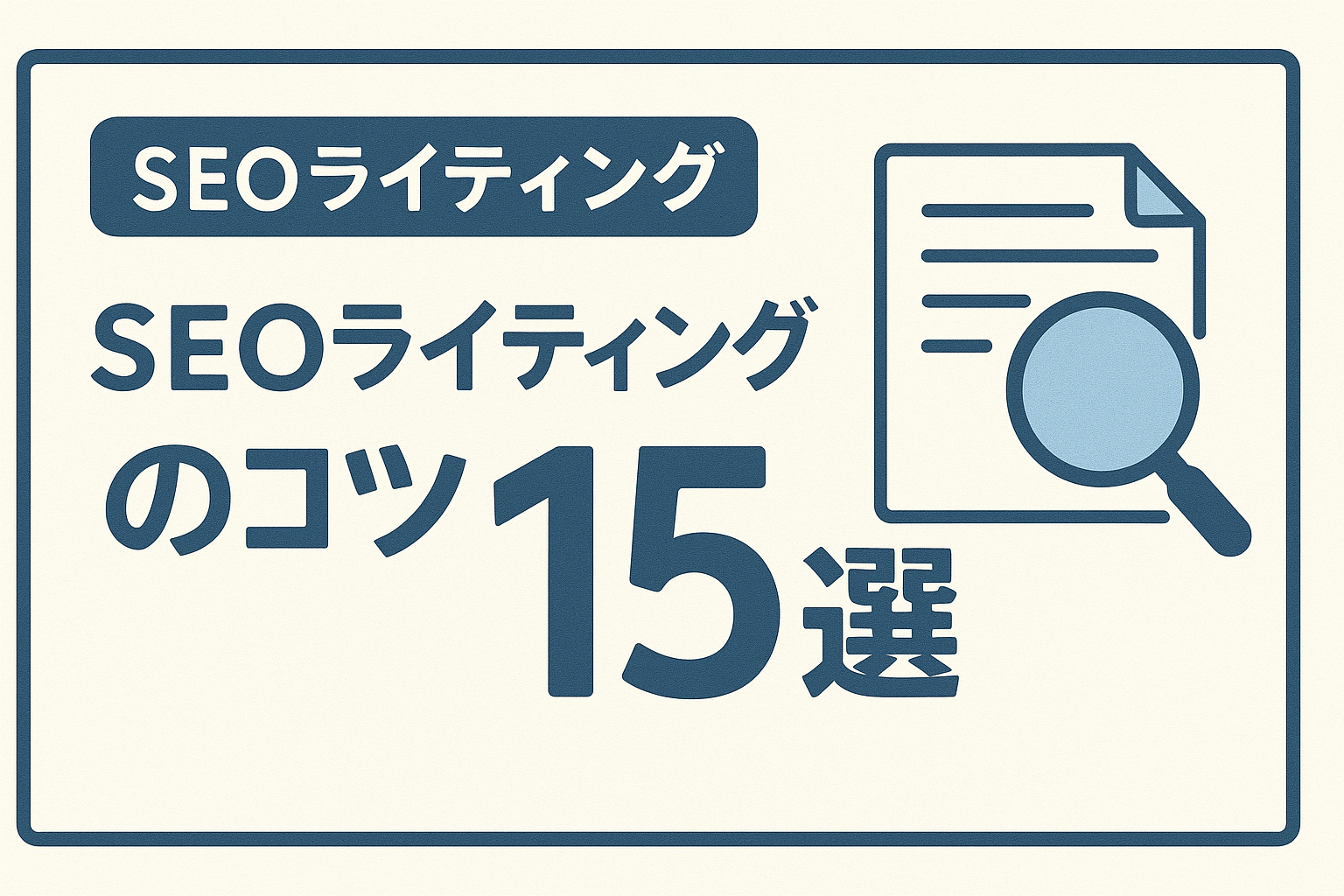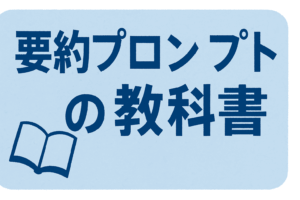「SEOライティングのコツを知りたいけど、何から学べばいいかわからない…」
「頑張って記事を書いているのに、一向に検索順位が上がらない…」
このような悩みをお持ちではありませんか?この記事では、SEO歴20年の専門家が、ライティング初心者の方でもプロ級の記事が書けるようになる「SEOライティングの15のコツ」を、準備から執筆、公開後の改善まで全手順に沿って徹底解説します。
この記事を読み終える頃には、小手先のテクニックではない、Googleと読者の両方から愛される記事作成の本質が理解でき、自信を持ってライティングに取り組めるようになっているはずです。
まず結論!SEOに強い記事の「たった一つの本質」と成果までの全手順マップ
SEOライティングには様々なテクニックが存在しますが、突き詰めるとその本質は非常にシンプルです。ここでは、すべてのテクニックの土台となる「たった一つの本質」と、成果を出すまでの具体的な全手順を最初に解説します。
SEOライティングで最も重要な本質は、ユーザーの検索意図に完璧に応えることです。なぜなら、Googleの目的は「ユーザーの疑問や悩みに最も的確に、そして分かりやすく答えているページを上位に表示すること」だからです。小手先のテクニックで検索エンジンを騙すことは、もはや不可能です。
例えば、「肌荒れ 改善」と検索したユーザーは、改善策だけでなく、肌荒れの原因や予防法、おすすめのスキンケア商品まで知りたいかもしれません。この「ユーザーが知りたいであろう情報の全体像」を先回りして提供することが、検索意図に応えるということです。
この記事では、その本質を体現するための具体的な15のコツを、以下の手順マップに沿って解説していきます。
- 【準備・戦略編】:キーワード選定、検索意図分析、ペルソナ設定など
- 【執筆・実践編】:タイトル作成、導入文、本文ライティングなど
- 【改善・分析編】:公開後の効果測定とリライト
この手順通りに進めれば、誰でも再現性高く、質の高いSEO記事を作成できます。
AIライティングの全手順を動画で体系的に学ぶなら、私たちの『7日間無料講座』が最適です。詳細はこちらからご確認ください。
【準備・戦略編】成果の8割が決まるSEOライティングの5つの基本戦略
本格的な執筆に入る前の「準備・戦略」フェーズは、SEOライティングの成果を8割方決定づける最も重要な段階です。多くの初心者はこの準備を怠り、いきなり書き始めてしまうため失敗します。ここでは、盤石な土台を築くための5つの基本戦略を解説します。
1.【経営視点】売上から逆算する「勝てるキーワード」の選定方法
SEOライティングにおけるキーワード選定とは、自社の売上や利益に直結するキーワードを見つけ出す作業のことです。単に検索数の多いキーワードを狙うのは、初心者が陥りがちな間違いです。
なぜなら、ビジネスの最終目的はアクセスを集めることではなく、利益を上げることだからです。例えば、あなたが都心で高級オーダースーツ店を営んでいる場合、「スーツ おすすめ」という検索数の多いキーワードよりも、「オーダースーツ 東京 高級」というキーワードの方が、購入意欲の高い、質の良い顧客にアプローチできます。
このように、自社のサービスや商品のターゲット顧客がどのような言葉で検索するかを考え、最終的なゴールから逆算してキーワードを選定することが、費用対効果の高いSEO施策に繋がります。
2. 検索意図を完璧に理解する競合上位10記事の“正しい”分析術
検索意図とは、ユーザーがそのキーワードで検索した「本当の目的」や「知りたいことの背景」を指します。これを理解することが、SEOライティングの成功の鍵を握ります。
ユーザーの目的を無視して記事を作成しても、内容が的外れになり、読者はすぐにページを閉じてしまうでしょう。そこで重要になるのが、競合上位記事の分析です。
対策したいキーワードで実際に検索し、上位10サイトの記事タイトルや見出しを一覧にしてみましょう。すると、「どのような情報(トピック)が」「どのような順番で」語られているか、共通のパターンが見えてきます。これが、Googleが「ユーザーが求めている答えのパッケージ」だと判断している内容、つまり検索意図の答えです。
3. たった一人に深く刺さる「ペルソナ設定」で独自性を生み出す
ペルソナ設定とは、記事を読んでほしい理想の読者像を、具体的かつ詳細に設定することです。「20代女性」のような曖昧なターゲットではなく、「都内で働く28歳、営業職の女性。最近、乾燥とニキビに悩み、根本的な肌質改善を目指している」というレベルまで具体化します。
なぜなら、たった一人に向けて書かれた手紙のように、具体的な人物像を思い描いて書くことで、文章に熱意と具体性が宿り、結果的に多くの人の心に響くコンテンツになるからです。「みんな」に向けて書いた文章は、誰の心にも刺さりません。
設定したペルソナが抱える悩みや疑問に寄り添い、「〇〇さん、こんなことで悩んでいませんか?」と語りかけるように書くことで、ありきたりな記事にはない、あなただけの独自性が生まれます。
4. Googleが最重要視する「E-E-A-T」を記事に実装する方法
E-E-A-Tとは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trust(信頼性)の頭文字を取ったもので、Googleがコンテンツの品質を評価するための非常に重要な指標です。簡単に言えば、「その分野のプロが、実際の体験に基づいて、信頼できる情報を提供しているか?」という基準です。
これを記事に実装するには、まず「誰が書いているのか」を明確にすることが重要です。記事の筆者情報を明記し、その分野での経歴や実績を示しましょう。例えば、「元化粧品開発者が解説する」といった形です。
さらに、記事内では「私が実際に1ヶ月試した結果…」のような自身の体験談や、公的機関の統計データ、専門家の意見を引用することで、E-E-A-Tは格段に向上します。情報の正確性と信頼性を担保することが、読者とGoogleからの評価に繋がります。
5. 全体の設計図となる「構成案」を作成する重要性とテンプレート
構成案とは、記事全体の骨格となる「設計図」のことです。いきなり本文を書き始めるのではなく、まずタイトル、導入文、見出し(H2, H3)の流れを最初に決めることが、質の高い記事を効率的に書くための秘訣です。
設計図なしに家を建てられないのと同じで、構成案なしに記事を書くと、内容が重複したり、話の流れがちぐはぐになったりして、読みにくい記事になってしまいます。事前に構成案を作成することで、論理的で一貫性のある、読者がストレスなく読み進められる記事構造を作ることができます。
まずは競合分析で見えた検索意図を元に、ユーザーが知りたい情報を網羅する見出しを洗い出し、最も分かりやすい順番に並べ替えることから始めましょう。この構成案さえしっかり作れば、ライティング作業の半分は終わったと言っても過言ではありません。
AIライティングの全手順を動画で体系的に学ぶなら、私たちの『7日間無料講座』が最適です。詳細はこちらからご確認ください。
【執筆・実践編】読者とGoogleに評価される7つのライティングテクニック
盤石な準備ができたら、いよいよ執筆の実践編です。ここでは、読者の心を掴んで離さず、Googleからも正しく評価されるための具体的なライティングテクニックを7つ紹介します。一つひとつを意識するだけで、記事のクオリティは劇的に向上します。
1. クリック率が2倍になる「最強のタイトル」4つの型
記事タイトルは、検索結果画面でユーザーが最初に目にする、いわばお店の「看板」です。どんなに素晴らしい内容でも、タイトルが魅力的でなければクリックされず、読まれることすらありません。
クリックされやすいタイトルには、いくつかの「型」があります。以下の4つの型を組み合わせることで、クリック率(CTR)を大きく改善できます。
- 数字を入れる:「5つのコツ」「3つのステップ」など、具体性が増し、情報が整理されている印象を与える。
- ベネフィットを提示する:「〜できる」「〜になる方法」など、読者が得られる未来を想像させる。
- 簡単な言葉を使う:「初心者でも」「たった3分で」など、行動のハードルを下げる。
- キーワードを入れる:最も重要なキーワードは、タイトルの前半に入れるのが基本。
(例)SEOライティングのコツ → 【初心者でもプロ級】SEOライティングのコツ15選!完全ガイド
2. 読者の離脱を9割防ぐ「導入文(リード文)」の鉄板テンプレート
導入文(リード文)は、読者がその記事を読み進めるか、それとも離脱するかを決める非常に重要な部分です。ここで読者の心を掴めなければ、本文が読まれることはありません。
成果の出る導入文は、以下のテンプレートに沿って書くのが効果的です。
- 悩みの提示と共感:「〇〇で悩んでいませんか?」と読者の悩みを代弁し、共感を示す。
- 記事を読むメリットの提示:「この記事を読めば、〇〇が解決できます」と、得られる結果(ベネフィット)を明確に伝える。
- 内容の要約:記事全体でどのような内容が語られるのかを簡潔に示す。
- 信頼性の提示:「SEO専門家が解説します」など、記事の信頼性をアピールする。
この流れに沿って書くことで、読者は「この記事は自分のためのものだ」「読む価値がありそうだ」と感じ、スムーズに本文へと読み進めてくれます。
3. 本文がスラスラ読める論理的な「見出し構成(H2,H3)」の作り方
見出しは、長文の記事における「道しるべ」の役割を果たします。適切な見出し構成は、読者が内容を瞬時に把握し、自分の読みたい箇所へジャンプする手助けをします。
見出しはH2、H3、H4…と階層構造になっており、これは本の「章」「節」「項」と同じです。H2という大きなテーマの中に、関連するH3という小さなテーマが含まれるように、論理的な親子関係を意識して作成することが重要です。
例えば、「SEOライティングのコツ(H2)」の中に「タイトルの付け方(H3)」「導入文の書き方(H3)」が入るのは自然ですが、「筆者のプロフィール(H3)」が入るのは不自然です。読者と検索エンジンの両方が、記事の構造を直感的に理解できるよう、常に論理的な流れを意識しましょう。
4. 専門家でなくても説得力が増す「PREP法」を活用した文章術
PREP法とは、Point(結論)、Reason(理由)、Example(具体例)、Point(結論の再提示)の順で文章を構成するフレームワークです。この型に沿って書くことで、誰でも驚くほど分かりやすく、説得力のある文章を作成できます。
特に専門的な内容を解説する際に有効で、まず最初に結論を述べることで、読者は「この記事は何について書かれているのか」をすぐに理解できます。その後に理由と具体例が続くため、内容への納得感も高まります。
(例)
P(結論):SEOライティングではPREP法が有効です。
R(理由):なぜなら、結論から話すことで、読者が最も知りたい情報を最初に伝えられるからです。
E(具体例):この記事の各見出しも、PREP法を意識して構成されています。
P(結論):このように、PREP法を使えば、論理的で分かりやすい文章を書くことができます。
5. ツールで簡単!共起語・関連キーワードを“自然に”盛り込むコツ
共起語とは、あるキーワードと一緒に使われることの多い単語のことです。例えば、「SEO」というキーワードであれば、「対策」「キーワード」「コンテンツ」「Google」などが共起語にあたります。
共起語を記事に含めることで、トピックの網羅性が高まり、検索エンジンが「この記事はこのテーマについて詳しく書かれているな」と認識しやすくなります。ただし、不自然に詰め込むのは逆効果です。
無料の共起語抽出ツールなどを活用し、どのような単語が必要かリストアップしましょう。そして、それらの単語を無理やり入れるのではなく、「この説明をするなら、自然とこの単語も使うな」という視点で、文章の流れを意識しながら盛り込んでいくのがコツです。
6. サイト全体の評価を高める「内部リンク」の戦略的な配置方法
内部リンクとは、自分のサイト内のページ同士を繋ぐリンクのことです。この記事から、サイト内の別の関連記事へリンクを貼ることを指します。
内部リンクを適切に設置することには、2つの大きなメリットがあります。1つは、読者が関連情報へスムーズに移動できるため、サイト内での滞在時間が延び、満足度が向上すること。もう1つは、検索エンジンのクローラー(サイトを巡回するロボット)がサイト内を巡回しやすくなり、各ページの関連性を正しく認識させ、サイト全体の評価を高める効果があることです。
「より詳しい〇〇については、こちらの記事で解説しています」といった形で、読者の理解を助ける文脈で、自然に設置するのがポイントです。
7.【最重要】AIには書けない「一次情報(独自性)」の加え方
一次情報とは、あなた自身の体験や経験、独自の調査結果、専門家としての考察など、他のサイトにはないオリジナルの情報のことです。これが、競合記事との最大の差別化要因になります。
現代では、AIを使えば誰でもそれらしい文章を生成できます。だからこそ、Googleはコピーコンテンツのようなありきたりな情報ではなく、筆者の血の通った、独自性のある情報を高く評価します。
例えば、「私が実際にこのツールを使ってみて感じたメリット・デメリット」「クライアントの成功事例」「100人にアンケート調査した結果」といった情報は、あなたにしか書けない貴重な一次情報です。このような独自の情報こそが、読者にとって本当に価値のあるコンテンツとなります。
AIライティングの全手順を動画で体系的に学ぶなら、私たちの『7日間無料講座』が最適です。詳細はこちらからご確認ください。
【改善・分析編】書いた記事を「永続的な資産」に変える3つのリライト術
SEOライティングは、記事を公開したら終わりではありません。むしろ、公開してからが本当のスタートです。ここでは、公開した記事の効果を測定し、改善を繰り返すことで、永続的にアクセスを生み出す「資産」へと育てていくための3つのリライト術を解説します。
1. 無料ツールでOK!公開後の効果測定と分析の基本
記事を公開したら、必ず「Googleサーチコンソール」という無料ツールを使って効果測定を行いましょう。このツールを使えば、「どのキーワードで」「何回表示され(表示回数)」「何回クリックされたか(クリック数)」「検索結果の何位にいるか(掲載順位)」といったデータを確認できます。
これらのデータを分析することで、ユーザーのリアルな反応を知ることができます。例えば、「表示回数は多いのにクリック数が少ない」のであれば、タイトルに魅力がないのかもしれません。「クリック数は多いのに順位が低い」のであれば、記事の内容に改善の余地がある、といった仮説を立てることができます。
感覚で記事を改善するのではなく、このような客観的なデータに基づいて、次の打ち手を考えることが重要です。
2. 順位が伸び悩む記事を蘇らせる「リライト」の具体的な手順
リライトとは、公開済みの記事を修正・追記して、より質の高いコンテンツに作り直すことです。情報が古くなったり、新しい競合記事が登場したりするため、定期的なリライトは順位維持・向上のために不可欠です。
リライトの基本的な手順は以下の通りです。
- キーワードで再検索:現在の競合上位記事を改めて分析し、自分の記事に足りない情報やトピックがないか確認する。
- 情報の追加・更新:足りない情報を追記し、古い情報を最新のものに更新する。
- 分かりやすさの改善:図解を追加したり、専門用語をより平易な言葉に直したりして、可読性を高める。
特に、公開後3ヶ月ほど経っても順位が10位〜30位あたりで停滞している記事は、リライトによって大きく順位がジャンプアップする可能性を秘めています。
3. 低コストで流入を増やす「CTR(クリック率)改善」の裏ワザ
CTR(Click Through Rate)とは、検索結果に表示された回数のうち、実際にクリックされた割合のことです。CTRを改善することは、記事の内容を一切変更せずに、アクセス数を増やすことができる非常に費用対効果の高い施策です。
CTRが低い原因のほとんどは、タイトルとディスクリプション(検索結果でタイトルの下に表示される説明文)にあります。特に、検索順位がすでに10位以内にあるにも関わらずCTRが低い場合は、タイトルをより魅力的なものに変更するだけで、クリック数が1.5倍〜2倍になることも珍しくありません。
前述した「最強のタイトルの4つの型」を参考に、数字やベネフィットを盛り込んだり、読者の興味を引くようなキャッチーな言葉を入れたりして、複数のパターンをテストしてみましょう。
AIライティングの全手順を動画で体系的に学ぶなら、私たちの『7日間無料講座』が最適です。詳細はこちらからご確認ください。
【経営者・責任者向け】SEOライティングの費用対効果を最大化する2つの視点
コンテンツ作成を事業として捉える経営者やWeb責任者の方にとっては、その費用対効果(ROI)が最も重要な関心事でしょう。ここでは、SEOライティングへの投資を最大化するための2つの重要な視点を、プロのコンサルタントとして解説します。
1. 内製化と外注はどちらが正解?メリット・デメリットと判断基準
SEOライティングを社内で行うか(内製化)、外部のプロに依頼するか(外注)は、多くの企業が悩むポイントです。どちらが正解ということはなく、企業の状況によって最適な選択は異なります。
それぞれのメリット・デメリットは以下の通りです。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 内製化 | ・コストが抑えられる ・自社の商品知識が深い ・ノウハウが社内に蓄積する | ・専門知識を持つ人材の確保/育成が難しい ・品質が属人化しやすい |
| 外注 | ・プロ品質の記事が手に入る ・社内リソースを割かなくて済む ・客観的な視点を取り入れられる | ・コストがかかる ・自社の深い理解を得るのに時間がかかる |
判断基準としては、長期的にコンテンツに注力し、社内にノウハウを蓄積したいなら「内製化」、すぐにでも高品質な記事で成果を出したいなら「外注」を検討するのが良いでしょう。
2.「良いライター・悪いライター」を1分で見抜く品質チェックリスト
外注する際に最も重要なのは、信頼できる「良いライター」を見極めることです。料金だけで選んでしまうと、品質の低い記事が納品され、かえって時間とコストを無駄にしかねません。
以下のチェックリストを使えば、ライターの品質を簡単に見抜くことができます。
- 実績の提示:過去に執筆した記事(特に記名記事)や、SEOでの実績を具体的に提示できるか?
- 構成案の質:依頼前に、こちらの意図を汲んだ質の高い構成案を作成できるか?
- コミュニケーション:質問への回答が的確か?レスポンスは迅速で丁寧か?
- 専門性:依頼するジャンルに関する専門知識や資格を持っているか?
特に、構成案の作成を依頼してみるのが最も効果的です。構成案を見れば、そのライターの検索意図の読解力や論理的思考力が一目瞭然となります。
AIライティングの全手順を動画で体系的に学ぶなら、私たちの『7日間無料講座』が最適です。詳細はこちらからご確認ください。
SEOライティングで初心者がやりがちな失敗例と注意点
ここでは、多くの初心者が無意識にやってしまいがちな、SEO評価を下げる典型的な失敗例を4つ紹介します。これらを避けるだけで、ライバルに差をつけることができます。
1. キーワードをとにかく詰め込みすぎる(キーワードスタッフィング)
SEOを意識するあまり、対策キーワードを記事内に不自然なほど詰め込んでしまうのは、典型的な失敗例です。これを「キーワードスタッフィング」と呼び、Googleからペナルティを受ける原因にもなります。
昔のSEOでは有効なテクニックでしたが、現在のGoogleは文脈を理解する能力が非常に高いため、このような小手先のテクニックは通用しません。むしろ、読みにくさから読者の離脱を招き、評価を下げる結果になります。
キーワードは意識しつつも、あくまで読者が自然で読みやすいと感じる範囲に留めることが重要です。目安として、キーワード出現率は2〜3%程度が適切と言われています。
2. どこかで見たような内容のコピーコンテンツになっている
競合記事を参考にするあまり、内容や構成が酷似してしまい、独自性のないコピーコンテンツのようになってしまうのも、よくある失敗です。
上位記事の内容を参考にすることは重要ですが、それはあくまで「検索意図を理解するため」です。情報を丸写しするのではなく、必ずあなた自身の言葉で書き直し、独自の視点や体験談(一次情報)を加えることを忘れないでください。
「この記事でしか得られない情報」が一つでもあるか?という視点を常に持ち、他のどのサイトよりも詳しく、分かりやすく、そしてユニークな内容を目指すことが、Googleから高く評価される秘訣です。
3. 専門用語が多く、読者目線が欠けている
自分の専門分野について書く際に、つい専門用語を多用してしまい、初心者である読者を置き去りにしてしまうケースです。書き手にとっては当たり前の言葉でも、読者にとっては理解できない外国語と同じです。
専門用語を使う場合は、必ず初出時に「〇〇とは、〜のことです」と定義を説明し、その後「中学生でも分かるように言うと…」といった形で、簡単な言葉や具体例に置き換える配慮が必要です。
常に「この記事を読むのは、この分野について何も知らない初心者だ」という意識を持ち、相手の知識レベルに合わせた、徹底的な「読者目線」で執筆することが信頼に繋がります。
4. 記事を公開して満足し、リライト(改善)を行わない
渾身の記事を書き上げて公開し、それで満足してしまうのは、非常にもったいない失敗です。SEOライティングは、公開後のデータ分析と改善(リライト)こそが本番と言えます。
検索順位は、競合の動向やGoogleのアルゴリズムアップデートによって常に変動します。一度上位表示されても、何もしなければいずれ順位は落ちていきます。
定期的にGoogleサーチコンソールで順位やクリック率をチェックし、パフォーマンスが低下している記事や、伸び悩んでいる記事を見つけてリライトする習慣をつけましょう。記事を「育てる」という意識を持つことが、長期的に安定した成果を出すために不可欠です。
AIライティングの全手順を動画で体系的に学ぶなら、私たちの『7日間無料講座』が最適です。詳細はこちらからご確認ください。
SEOライティングに関するよくある質問(Q&A)
最後に、SEOライティングに関して初心者の方からよく寄せられる質問とその回答を、Q&A形式でまとめました。
Q1. 記事の最適な文字数はどれくらいですか?
A. 最適な文字数に絶対的な正解はありません。重要なのは「検索意図に答えるために必要な情報を網羅できているか」です。
上位表示されている競合記事が必要な情報を3,000字で解説しているなら、あなたの記事も同等以上の情報量が必要になります。逆に、競合が10,000字で冗長に解説している内容を、より分かりやすく5,000字でまとめられるなら、それでも評価される可能性はあります。
結論として、文字数を目標にするのではなく、ユーザーの疑問に完璧に答えた結果、必要な文字数になった、と考えるのが正しいアプローチです。
Q2. AIライティングツールを使ってもGoogleの評価は落ちませんか?
A. Googleは、AIによって生成されたかどうかではなく、「コンテンツの品質」で評価すると公言しています。したがって、AIを使っても品質が高ければ問題ありません。
ただし、AIが生成した文章をそのまま公開するのは危険です。事実確認が不十分であったり、独自性が欠けていたりすることが多いためです。AIはあくまで「優秀なアシスタント」として活用し、最終的には人間が責任を持って、一次情報の追加や編集、ファクトチェックを行うことが不可欠です。
AIをうまく活用することで、ライティングの効率を大幅に向上させることは可能です。
Q3. 効果が出るまで、どれくらいの期間がかかりますか?
A. 一概には言えませんが、一般的に3ヶ月から6ヶ月、場合によっては1年以上の期間が必要になることもあります。
効果が出るまでの期間は、サイトのドメインパワー(信頼性)、対策するキーワードの競合の強さ、コンテンツの品質など、様々な要因に左右されます。新規で立ち上げたばかりのサイトであれば、Googleに認識され、評価が安定するまでにある程度の時間が必要です。
SEOは短期的な結果を求めるものではなく、良質なコンテンツという資産をコツコツと積み上げていく、長期的な施策であると理解することが重要です。
Q4. おすすめのSEOライティングツールはありますか?
A. 目的によって様々なツールがありますが、初心者の方がまず揃えるべき基本ツールは以下の通りです。
- キーワード選定ツール:Ubersuggest, Googleキーワードプランナー (無料)
- 競合分析・順位チェック:GRC (有料だが安価), Ahrefs (高機能・高価)
- 共起語抽出ツール:ラッコキーワード (無料)
- コピーコンテンツチェック:CopyContentDetector (無料)
まずは無料のツールから試してみて、必要に応じて有料ツールの導入を検討するのが良いでしょう。これらのツールを使いこなすことで、ライティングの効率と品質を大きく向上させることができます。
AIライティングの全手順を動画で体系的に学ぶなら、私たちの『7日間無料講座』が最適です。詳細はこちらからご確認ください。
まとめ:小手先のテクニックを卒業し、読者に価値を届ける「本質的なSEOライティング」を始めよう
本記事では、初心者の方がプロ級の記事を書くためのSEOライティングのコツを、準備から執筆、改善までの全15ステップで解説しました。
数多くのテクニックを紹介しましたが、最も重要な本質は、常に「ユーザーの検索意図に完璧に応えること」、これに尽きます。読者が何に悩み、何を知りたいのかを徹底的に考え抜き、その答えを誰よりも分かりやすく、そして信頼できる形で提供すること。この姿勢こそが、Googleと読者の両方から評価される唯一の道です。
この記事で紹介したコツを一つでも多く実践し、読者に「この記事に出会えてよかった」と思ってもらえるような、価値あるコンテンツ作成を今日から始めてみましょう。
AIライティングの全手順を動画で体系的に学ぶなら、私たちの『7日間無料講座』が最適です。詳細はこちらからご確認ください。