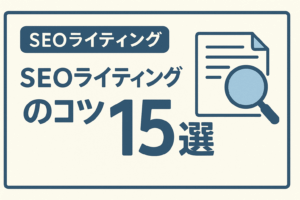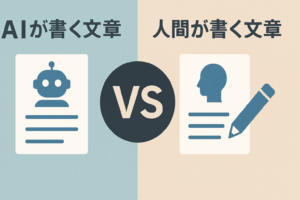「SEOライティングのやり方が分からず、何から手をつければいいか悩んでいる」「頑張って記事を書いているのに、まったく検索順位が上がらない…」そんなお悩みはありませんか?
この記事では、SEOのプロが実践している具体的な7つの手順と、明日から使える15のコツを初心者向けに徹底解説します。この記事を最後まで読めば、読者とGoogleの両方から評価される記事作成の全工程が理解でき、自信を持って上位表示を目指せるようになります。
まずは結論:SEOライティングで成果を出すための7つの手順
SEOライティングで成果を出すためには、闇雲に書き始めるのではなく、決まった手順に沿って進めることが成功への近道です。ライティングは「準備」と「設計」の段階で、その品質の9割が決まります。
この記事で解説する、成果を出すための具体的な手順は以下の7つです。
- 手順1:【準備】キーワード選定と検索意図の分析
- 手順2:【設計】上位表示を左右する構成案の作成
- 手順3:【執筆】読者とGoogleに評価される本文ライティング
- 手順4:【装飾】読みやすさを向上させるテクニック
- 手順5:【校正】公開前に質を高める最終チェック
- 手順6:【設定】検索エンジンに正しく伝えるための施策
- 手順7:【改善】公開後に成果を最大化するリライト
これらの手順を一つずつ丁寧に行うことで、初心者の方でも着実に成果の出る記事を作成できます。
AIライティングの全手順を動画で体系的に学ぶなら、私たちの『7日間無料講座』が最適です。詳細はこちらからご確認ください。
そもそもSEOライティングとは?成果を出すために知るべき3つの基本
具体的な手順に入る前に、まずは「SEOライティング」そのものについて理解を深めましょう。基本的な考え方を知ることで、この後のテクニックがなぜ重要なのか腹落ちし、応用力も身につきます。
ここでは、成果を出すために最低限知っておくべき3つの基本を解説します。
1. 通常のライティングとの決定的な違い
結論として、SEOライティングと通常のライティングの決定的な違いは、「主な読者が『人間』と『検索エンジン』の2者であること」を意識するかどうかです。
通常のライティングは、人間の読者にとって分かりやすく、心を動かす文章を書くことがゴールです。一方、SEOライティングでは、その内容を検索エンジン(Googleなど)にも正しく理解してもらい、高く評価してもらう必要があります。
例えば、素晴らしい小説でも、検索エンジンが「この記事は何について書かれているか」を理解できなければ、検索結果に表示されません。SEOライティングは、読者の満足度を最大化しつつ、検索エンジンにも配慮した、いわば「二兎を追う」技術なのです。
2. コンテンツが「Web上の資産」になる理由
良質なSEOライティングで作成されたコンテンツは、単なる記事ではなく、「Web上の資産」として継続的に価値を生み出します。
なぜなら、一度検索上位に表示された記事は、広告費をかけなくても24時間365日、自動で集客し続けてくれるからです。これは、時間と共に価値が目減りする広告とは対照的です。まるで、インターネット上に優秀な営業マンを雇ったり、好立地に不動産を持ったりするようなものだと考えてください。
初期投資として制作コスト(時間や費用)はかかりますが、長期的に見れば、広告よりもはるかに費用対効果の高い施策となり得ます。そのため、多くの企業がコンテンツを「資産」と捉え、SEOライティングに力を入れているのです。
3. Googleに評価される大原則「E-E-A-T」とは
E-E-A-T(ダブルイーエーティー)とは、Googleがコンテンツの品質を評価するための非常に重要な指標です。これは「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字を取ったものです。
簡単に言うと、「その情報は、実際に体験した人が、専門家として、その分野の権威として、信頼できる情報源を基に語っているか?」をGoogleが見ているということです。
例えば、病気の治療法について解説する記事なら、匿名のブロガーが書いた記事より、医師免許を持つ専門家が自身の臨床経験を基に執筆した記事の方がはるかに信頼できます。このように、記事の内容にE-E-A-Tを盛り込むことが、Googleからの高評価、ひいては検索上位表示に不可欠なのです。
AIライティングの全手順を動画で体系的に学ぶなら、私たちの『7日間無料講座』が最適です。詳細はこちらからご確認ください。
【完全攻略】SEOライティングのやり方7つの手順
ここからはいよいよ、SEOライティングの具体的なやり方を7つの手順に沿って解説します。この手順通りに進めれば、誰でも迷うことなく、質の高い記事を作成できます。一つひとつのステップを確実に実行していきましょう。
1. 【準備】キーワード選定と検索意図の分析
最初のステップは、読者がどんな言葉(キーワード)で検索し、その裏で何を求めているか(検索意図)を徹底的に分析することです。ここを間違えると、どんなに良い記事を書いても誰にも読まれません。
キーワード選定とは、読者が検索窓に打ち込むであろう単語やフレーズを見つけ出す作業です。例えば「SEOライティング」だけでなく、「SEOライティング やり方 初心者」といった、より具体的なキーワードを探します。
次に、そのキーワードで検索する人が「なぜ検索したのか?」を深く考えます。これが検索意図の分析です。「やり方を知りたい」だけでなく、「失敗したくない」「効率的に学びたい」といった隠れたニーズまで汲み取ることで、読者の心に響く記事が作れるのです。
2. 【設計】上位表示を左右する構成案の作成
キーワードと検索意図を明確にしたら、次は記事の設計図となる「構成案」を作成します。構成案は記事の骨格であり、この段階で記事の品質の9割が決まると言っても過言ではありません。
構成案とは、記事のタイトルや見出し(h2, h3)の順番を決める作業です。読者が知りたいであろう情報を、論理的で分かりやすい順番に並べていきます。これは、家を建てる前に設計図を描くのと同じくらい重要です。
良い構成案を作るコツは、まず対策キーワードで上位表示されている競合記事を複数チェックし、どのようなトピックが共通して含まれているかを分析することです。その上で、読者の疑問をさらに先回りして解決できるような独自の情報を加え、競合よりも優れた設計図を完成させます。
3. 【執筆】読者とGoogleに評価される本文ライティング
設計図が完成したら、いよいよ本文の執筆に入ります。ここでは、「読者の疑問に、誰よりも分かりやすく、そして深く答える」ことを常に意識してください。
まず、各見出し(h3)に対して、PREP法(結論→理由→具体例→まとめ)を意識して書くと、論理的で分かりやすい文章になります。専門用語を使う際は必ず初出で意味を説明し、中学生でも分かるような具体例を添えましょう。
また、Googleに「この記事は専門性が高い」と認識させるため、関連キーワードや共起語(そのテーマでよく一緒に使われる言葉)を不自然にならない程度に盛り込むことも大切です。ただし、キーワードの詰め込みすぎは逆効果なので、あくまで読者の読みやすさを最優先にしてください。
4. 【装飾】読みやすさを向上させるテクニック
文章の内容が良くても、文字がびっしりと詰まっているだけでは読者は疲れて離脱してしまいます。適度な装飾を施し、視覚的に読みやすい記事に仕上げることが重要です。
誰でも簡単にできる装飾の基本は3つです。1つ目は、2〜3文ごとに改行を入れて、余白を作ること。2つ目は、重要な部分を太字にして、メリハリをつけること。3つ目は、情報を整理するために箇条書きや表を使うことです。
例えば、複数の手順やメリット・デメリットを説明する際には、ただ文章で羅列するのではなく、箇条書きや表を使うだけで、読者の理解度は格段に上がります。これらの装飾は、読者の滞在時間を延ばし、SEO評価の向上にも繋がります。
5. 【校正】公開前に質を高める最終チェック
記事を書き終えたら、公開する前に必ず校正(文章のチェックと修正)を行いましょう。誤字脱字や不自然な表現は、読者の信頼を損ない、サイト全体の評価を下げる原因になります。
校正の際は、最低でも以下の3つの視点でチェックしてください。1つ目は「誤字脱字」。声に出して読む「音読」をすると、黙読では気づきにくいミスを発見しやすくなります。2つ目は「文章のねじれ」。主語と述語が対応しているか、一文が長すぎないかを確認します。
3つ目は「情報の正確性」。特に数字や固有名詞、専門的な情報に間違いがないか、信頼できる情報源(公式サイトなど)と照らし合わせて再確認することが不可欠です。無料の校正ツールも活用し、記事の品質を極限まで高めましょう。
6. 【設定】検索エンジンに正しく伝えるための施策
質の高い記事が完成したら、その内容を検索エンジンに正しく伝えるための最終設定を行います。この設定を怠ると、せっかくの記事がGoogleに正しく評価されない可能性があります。
具体的には、主に3つの設定を行います。1つ目は「タイトルタグ」。これは検索結果に表示される記事の表題で、30文字程度で記事の内容が分かり、クリックしたくなるような魅力的なものにします。2つ目は「メタディスクリプション」。検索結果のタイトルの下に表示される説明文で、120文字程度で記事の要約と読むメリットを伝えます。
3つ目は「altタグ(代替テキスト)」。記事内の画像が表示されなかった場合に代わりに表示されるテキストで、画像の内容を簡潔に説明します。これらの設定は、検索エンジンとユーザーの両方に対する「道しるべ」の役割を果たします。
7. 【改善】公開後に成果を最大化するリライト
SEOライティングは、記事を公開したら終わりではありません。公開後の成果を分析し、記事を改善(リライト)し続けることで、資産価値を最大化できます。
なぜなら、読者のニーズや競合サイトの状況、Googleの評価基準は常に変化し続けるからです。定期的に記事の健康診断を行い、時代に合わせてアップデートしていく必要があります。
具体的には、「Googleサーチコンソール」などのツールを使って、記事の検索順位や表示回数、クリック率などをチェックします。もし順位が伸び悩んでいる場合は、「情報が古い」「読者の疑問に答えきれていない」などの原因を分析し、文章の追記や修正、新しい情報の追加といったリライトを行いましょう。この地道な改善が、長期的な成功に繋がります。
AIライティングの全手順を動画で体系的に学ぶなら、私たちの『7日間無料講座』が最適です。詳細はこちらからご確認ください。
明日から使える!SEOライティングの質を高める15のコツ
基本的な手順をマスターしたら、次はライティングの質をさらに一段階引き上げるための具体的なコツを学びましょう。ここでは、プロが実践している15のコツを「キーワード・構成」「執筆」「仕上げ」の3つのカテゴリーに分けて紹介します。できるものから取り入れてみてください。
キーワード・構成のコツ
1. サジェストキーワードで読者の悩みを深掘りする
サジェストキーワードとは、検索窓にキーワードを入力した際に自動で表示される候補のことで、多くの人が検索している組み合わせです。これを活用することで、読者の具体的な悩みを深掘りできます。
例えば、「SEOライティング」と入力すると、「やり方」「コツ」「初心者」「ツール」などが表示されます。これは、「やり方やコツを知りたい初心者で、便利なツールも探している」という読者像を浮かび上がらせます。
これらのサジェストキーワードを記事の見出しや内容に盛り込むことで、読者が「そうそう、それが知りたかった!」と感じる、かゆいところに手が届く記事になります。読者の悩みに寄り添うことが、満足度向上の第一歩です。
2. 再検索キーワードで潜在ニーズを捉える
再検索キーワードとは、あるキーワードで検索した人が、その次に検索し直したキーワードのことです。これは、最初の検索で満足できず、さらに知りたいと感じた「潜在的なニーズ」を示唆しています。
例えば、「SEOライティング やり方」で検索した人が、次に「SEOライティング 構成案 テンプレート」と検索したとします。これは、「やり方は分かったけど、構成案を作る具体的なテンプレートが欲しい」という隠れたニーズがあることを示しています。
この再検索キーワードを分析し、記事内に先回りして盛り込むことで、読者は他のサイトに移動することなく、あなたの記事だけで全ての疑問を解決できます。これにより、サイトの滞在時間が延び、Googleからの評価も高まります。
3. 競合分析で差別化ポイントを見つける
高品質な記事を作るためには、すでに上位表示されている競合サイトを分析し、自社記事の差別化ポイントを見つけることが不可欠です。
まずは、対策キーワードで検索上位10位までの記事を読み込み、どのようなトピックが網羅されているか、どのような切り口で書かれているかをリストアップします。これにより、読者が最低限求めている情報の基準が分かります。
その上で、「競合が触れていない新しい視点はないか?」「もっと初心者向けに分かりやすく解説できないか?」「自社の独自データや経験談を加えられないか?」と考えます。競合と同じ土俵で戦うのではなく、独自の価値を提供することで、あなたの記事が選ばれる理由が生まれるのです。
4. PREP法で論理的な文章構成を作る
PREP(プレップ)法とは、Point(結論)→ Reason(理由)→ Example(具体例)→ Point(結論の再提示)の順で文章を構成するフレームワークです。この型を使うことで、誰でも驚くほど論理的で分かりやすい文章が書けます。
ビジネスシーンでも多用されるこの手法は、最初に結論を伝えるため、読者は「この記事が何を言いたいのか」をすぐに理解できます。そして理由と具体例でその結論が補強されるため、内容への納得感が高まります。
例えば、この記事の各見出しもPREP法を意識して作られています。見出しごとにこの型を繰り返すだけで、記事全体の説得力が格段に向上します。初心者の方は、まずこのPREP法を徹底的に真似することから始めるのがおすすめです。
5. 独自性(一次情報・経験談)を盛り込む
Googleが近年とくに重視しているのが、コンテンツの独自性です。他サイトの情報をまとめただけのリライト記事ではなく、あなた自身の経験や考察に基づいた一次情報を加えることで、記事の価値は飛躍的に高まります。
一次情報とは、あなた自身が体験したこと、独自に調査したアンケート結果、専門家として得た知見など、他では得られないオリジナルの情報のことです。ありふれた情報の中に、こうした独自の情報が少し加わるだけで、記事に深みと信頼性が生まれます。
例えば、「実際にこの方法を試したら、3ヶ月で順位がこう変わった」という具体的な経験談や、「クライアントからよく受ける質問はこれです」といった現場の声は、非常に価値の高い一次情報です。自分にしか書けないことは何かを常に意識しましょう。
執筆のコツ
6. 結論(結論)から書き始める
読者は非常にせっかちで、自分の知りたい答えがすぐに見つからないと判断すると、即座にページを離れてしまいます。そのため、各見出しの冒頭では、必ず「結論」から書き始めることを徹底してください。
これは前述したPREP法の一部ですが、執筆時に特に意識すべき重要なポイントです。読者は「この見出しを読めば何が分かるのか?」を瞬時に判断したいと考えています。
例えば、「SEOライティングのコツ」という見出しであれば、「SEOライティングで最も重要なコツは、読者の悩みを解決することです」と最初に言い切ります。理由や具体例を長々と説明する前に結論を示すことで、読者は安心して続きを読むことができ、離脱率の低下に繋がります。
7. 中学生でもわかる平易な言葉を選ぶ
専門的な内容を扱う際でも、可能な限り専門用語を避け、中学生でも理解できるような平易な言葉で説明することが、より多くの読者に読んでもらうための秘訣です。
ライターは専門知識があるため、無意識に難しい言葉を使いがちです。しかし、読者の知識レベルは様々であり、専門用語が並んでいるだけで「この記事は難しそうだ」と敬遠されてしまう可能性があります。
どうしても専門用語を使わなければならない場合は、必ず初出で辞書的な意味を説明し、その直後に「簡単に言うと、〇〇のようなものです」「例えば、身近な△△で例えると…」といった形で、具体的な比喩や言い換えをセットで記述しましょう。このひと手間が、読者の理解を大きく助けます。
8. 共起語を自然に含めて専門性を高める
共起語とは、あるキーワードと一緒に使われることが多い単語のことで、これを記事内に自然に盛り込むことで、Googleにテーマとの関連性や専門性の高さを示すことができます。
例えば、「SEOライティング」というキーワードであれば、「キーワード」「構成」「見出し」「リライト」「ツール」といった単語が共起語にあたります。これらの単語が適切に含まれていると、Googleは「この記事はSEOライティングについて多角的に詳しく解説しているな」と判断しやすくなります。
ただし、共起語を無理やり詰め込むのは絶対にやめましょう。あくまで読者にとって分かりやすい文章の流れを最優先し、その中で自然に使える単語を選んで配置していくのがコツです。無料の共起語分析ツールなどを活用すると便利です。
9. 具体例やデータを用いて説得力を出す
抽象的な主張や説明だけでは、読者の共感や納得を得ることは困難です。具体的なエピソードや客観的な数値を盛り込むことで、文章の説得力は劇的に向上します。
例えば、「SEOは重要です」とだけ書かれていても、読者には響きません。しかし、「ある調査によれば、検索結果の1位のクリック率は28.5%ですが、10位になるとわずか2.5%にまで低下します」といった具体的なデータを提示されると、その重要性がリアルに伝わります。
また、「このツールは便利です」と書くよりも、「このツールを使って作業時間を月10時間削減できたクライアントがいます」という具体例を挙げる方が、読者は自分ごととして捉えやすくなります。主張には必ず具体例かデータをセットにすることを心がけましょう。
10. 適度に改行や箇条書きを使い、リズムを作る
PCやスマートフォンで文章を読む際、読者は文字の塊に強い圧迫感を覚えます。2〜3文ごとを目安にこまめに改行し、箇条書きを効果的に使うことで、文章に心地よいリズムが生まれます。
特にスマートフォンでの閲覧を意識することが重要です。PC画面では気にならなくても、スマホの小さな画面では5行以上の文章の塊は「文字の壁」に見え、読者の読む気を削いでしまいます。適度な改行は、読者の目線をスムーズに誘導し、ストレスを軽減する効果があります。
また、3つ以上の項目を列挙する場合は、文章で繋ぐよりも箇条書き(リスト)にした方が、情報が整理されて格段に読みやすくなります。「例えば、以下の3つのポイントがあります」と前置きし、リスト形式で示す癖をつけましょう。
h4:仕上げのコツ
11. オリジナル画像や図解で理解を助ける
「百聞は一見に如かず」という言葉通り、複雑な概念や手順を説明する際には、文章だけでなく、画像や図解を用いることで読者の理解を飛躍的に高めることができます。
例えば、ツールの操作手順を説明する場合、文章だけで説明するよりも、実際の操作画面のスクリーンショットを掲載した方が何倍も分かりやすくなります。また、概念的な関係性(例えばE-E-A-Tの各要素の関係など)は、シンプルな図で示すことで、直感的な理解を促せます。
フリー素材のイラストもお手軽ですが、可能であればオリジナルの図解を作成することをおすすめします。独自性のある画像は、他サイトとの差別化を図る上で非常に強力な武器となり、Googleからの評価も高まる傾向にあります。
12. 内部リンクでサイト全体の評価を高める
内部リンクとは、自身のサイト内の別ページへ設置するリンクのことです。これを戦略的に設置することで、ユーザーの利便性を高め、サイト全体のSEO評価を向上させることができます。
例えば、この記事の中で「キーワード選定」について触れた際に、キーワード選定の方法をより詳しく解説した別記事へのリンクを貼ります。これにより、読者は関連情報を求めてサイト内を回遊しやすくなり、サイトの滞在時間が増加します。
また、内部リンクは、Googleのクローラー(サイト情報を収集するロボット)がサイト内を巡回するのを助ける役割も果たします。関連性の高いページ同士をリンクで繋ぐことで、各ページのテーマ性がGoogleに伝わりやすくなり、サイト全体の評価向上に繋がるのです。
13. 音読して文章の違和感をチェックする
記事を書き終えた後、黙読するだけでなく、実際に声に出して読んでみる「音読」は、文章の不自然なリズムや誤りを発見するのに非常に効果的な方法です。
目で文字を追っているだけでは気づきにくい、読みにくい文章のリズム、不自然な接続詞の使い方、句読点の位置の違和感などを、耳で聞くことによって客観的に捉えることができます。音読して少しでも「つっかえる」箇所があれば、そこは読者も読みにくいと感じる可能性が高いです。
また、「ます」や「です」が連続しすぎて単調になっていないか、一文が長すぎて息継ぎが苦しくないか、といった点もチェックできます。少し恥ずかしいかもしれませんが、品質向上のためには欠かせない、プロも実践するテクニックです。
14. スマホでの見え方を必ず確認する
現在、Webサイトへのアクセスの大半はスマートフォン経由です。そのため、記事を公開する前に、必ずスマートフォンでの表示(見え方)を確認することは必須の作業です。
PCの大きな画面で執筆していると、レイアウトや文字の大きさが最適化されているように見えても、スマホで見ると印象が全く異なることがよくあります。文字が小さすぎたり、改行の位置が不自然だったり、画像が画面からはみ出していたりするかもしれません。
WordPressなどのCMSには、プレビュー機能でPC表示とスマホ表示を切り替える機能があります。読者が最も利用するデバイスでの見え方を最終チェックし、ストレスなく読める状態になっているかを確認する癖をつけましょう。
15. コピーコンテンツになっていないかツールで確認する
意図的でなくても、他サイトの記事と内容が酷似してしまうと、Googleから「コピーコンテンツ」とみなされ、サイト全体の評価を著しく下げられるペナルティを受ける危険性があります。
特に、様々なサイトを参考にして記事を作成していると、無意識のうちに表現が似通ってしまうことがあります。こうしたリスクを避けるため、記事公開前には必ずコピーコンテンツチェックツールを使って、他サイトとの類似度を確認しましょう。
無料・有料の様々なツールがありますが、これらを使えば、自身の記事とWeb上の既存記事とを比較し、一致率が高い箇所を指摘してくれます。もし一致率が高い部分が見つかった場合は、表現を修正したり、自身の言葉で書き直したりする対応が必要です。これは、サイトを守るための保険と言えます。
AIライティングの全手順を動画で体系的に学ぶなら、私たちの『7日間無料講座』が最適です。詳細はこちらからご確認ください。
作業効率が劇的に向上するSEOライティングツール7選
SEOライティングは、全てを手作業で行うと膨大な時間がかかります。幸いなことに、私たちの作業を助けてくれる便利なツールがたくさん存在します。ここでは、初心者でも使いやすく、作業効率を劇的に向上させてくれる定番ツールを7つ厳選して紹介します。
1. 【キーワード選定】ラッコキーワード / Ubersuggest
キーワード選定はSEOの出発点であり、これらのツールを使えば、関連キーワードを効率的に洗い出せます。ラッコキーワードは、一つのキーワードからサジェストキーワードや関連語を大量に取得できる無料ツールです。
一方、Ubersuggest(ウーバーサジェスト)は、キーワードの月間検索ボリューム(どのくらい検索されているか)や、競合の強さ(SEO難易度)まで調査できるのが特徴です。無料でも一部機能が使えますが、本格的に取り組むなら有料版も視野に入ります。
これらのツールを組み合わせることで、読者の需要があり、かつ上位表示を狙いやすい「お宝キーワード」を見つけ出すことが可能になります。まずは無料で使えるラッコキーワードから試してみるのがおすすめです。
2. 【構成作成】競合の見出し抽出ツール
構成案を作成する際、競合上位記事の見出しを一覧で比較・分析することは非常に重要です。手作業で一つずつコピー&ペーストするのは大変ですが、見出し抽出ツールを使えば一瞬で完了します。
ラッコキーワードには、指定したキーワードで検索上位20サイトの見出し(h1〜h4)を一覧で抽出する無料機能が備わっています。これを使えば、どのようなトピックが重要視されているのか、どのような構成が一般的なのかを一目で把握できます。
競合の優れた構成を参考にしつつ、自サイトならではの切り口や追加情報を盛り込むことで、より網羅的で質の高い構成案を効率的に作成できます。構成作成の時間を大幅に短縮できる、必須のツールです。
3. 【共起語分析】ラッコキーワード / ohotuku.jp
共起語を分析し、記事に盛り込むことで、専門性と網羅性を高めることができます。共起語とは、あるテーマについて語る上で、一緒に出現することが多い単語群のことです。
ラッコキーワードの共起語分析機能や、無料で使える「ohotuku.jp」などのツールを使えば、対策キーワードに対する共起語を簡単にリストアップできます。例えば「SEOライティング」の共起語として「タイトル」「コンテンツ」「リライト」などが抽出されます。
これらの単語を、執筆した本文に不足していないかチェックリストのように活用します。ただし、無理に詰め込むのではなく、あくまで自然な文脈で使うことが大切です。これにより、Googleに記事のテーマをより深く理解してもらうことができます。
4. 【コピーチェック】CopyContentDetector
意図しないコピーコンテンツのリスクを回避するため、公開前には必ずこのツールでチェックしましょう。CopyContentDetectorは、無料で高機能なコピーコンテンツチェックツールとして非常に有名です。
作成した記事のテキストをツールに貼り付けて実行するだけで、Web上の膨大なコンテンツと照合し、文章の一致率を判定してくれます。もし他サイトとの一致率が高い箇所が見つかった場合は、その部分を自分の言葉で書き直す必要があります。
悪意がなくとも、参考にした記事と表現が似てしまうことは誰にでも起こり得ます。このチェックを怠ると、サイト全体の評価を下げるペナルティに繋がりかねません。サイトを守るための必須作業として、必ず習慣づけましょう。
5. 【文章校正】Enno / Shodo
誤字脱字や不自然な日本語は、読者の信頼を損ないます。これらの校正ツールで文章の品質を高めましょう。Enno(エンノ)は、無料で利用できるシンプルな日本語校正ツールです。
文章を貼り付けるだけで、「ら抜き言葉」や二重敬語、誤った助詞の使い方などを素早く指摘してくれます。自分では気づきにくい細かなミスを減らし、文章の完成度を高めるのに役立ちます。
より高機能なものを求めるなら、AIが文脈を読んでより高度な提案をしてくれる「Shodo(ショドー)」などの有料ツールもあります。まずはEnnoのような無料ツールから始め、文章の品質チェックを効率化することをおすすめします。
6. 【順位確認】GRC / Nobilista
記事公開後は、その順位を定点観測し、リライトの判断材料にすることが重要です。GRCは、PCにインストールして使用するタイプの検索順位チェックツールで、古くから多くのSEO担当者に愛用されています。
指定したキーワードの順位を毎日自動で取得してくれるため、日々の変動や施策の効果を正確に把握できます。無料版もありますが、多くのキーワードを管理するなら有料版が必要です。
一方、Nobilista(ノビリスタ)は、PCにインストール不要で、ブラウザ上で使えるクラウド型のツールです。チームでの共有がしやすく、直感的なインターフェースが特徴です。どちらかのツールを導入し、データに基づいたサイト改善を行いましょう。
7. 【AIライティング】Gemini / ChatGPT
近年急速に発展しているAIライティングツールは、SEOライティングの様々な工程を効率化する強力なパートナーになります。GoogleのGeminiやOpenAIのChatGPTが代表的です。
これらのAIは、キーワードに対する構成案のアイデア出し、文章の要約やリライト、さらには本文の草案作成まで、幅広いタスクをこなせます。ゼロから考える時間を大幅に短縮し、ライターはより創造的な作業に集中できます。
ただし、AIが生成した文章をそのまま使うのは危険です。情報の正確性や独自性が欠けている場合があるため、必ず人間の目でファクトチェック(事実確認)と編集を行う必要があります。AIを「優秀なアシスタント」として賢く活用することが、今後のSEOライティングの鍵となるでしょう。
AIライティングの全手順を動画で体系的に学ぶなら、私たちの『7日間無料講座』が最適です。詳細はこちらからご確認ください。
これだけは避けたい!評価を下げるSEOライティングの3つの注意点
良かれと思ってやった施策が、実はGoogleからの評価を下げる原因になることがあります。ここでは、初心者が特に陥りがちな、絶対に避けるべき3つの注意点について解説します。これらの過ちを犯さないよう、常に念頭に置いておきましょう。
1. キーワードの詰め込みすぎ(キーワードスタッフィング)
上位表示させたいからといって、キーワードを不自然に詰め込みすぎる行為は逆効果です。これは「キーワードスタッフィング」と呼ばれる、Googleが明確に禁止しているスパム行為とみなされます。
例えば、「東京の格安SEOライティングなら、SEOライティング専門の当社へ。このSEOライティングサービスは…」のように、同じキーワードを何度も繰り返すと、文章が非常に読みにくくなります。
現在のGoogleは非常に賢く、文脈から記事のテーマを理解できます。キーワードは無理に詰め込むのではなく、あくまで読者が自然で読みやすいと感じる範囲で使用することを心がけてください。読者にとっての読みやすさが、結果的にSEO評価にも繋がります。
2. 独自性のない情報の羅列
他サイトから集めてきた情報を、ただ並べ替えてつなぎ合わせただけの記事は、Googleから低品質と判断されます。このような独自性のないコンテンツは、Web上に存在する価値がないと見なされてしまうのです。
Googleの目的は、ユーザーに多様で有益な情報を提供することです。どこにでもあるような同じ内容の記事ばかりが検索結果に並んでいては、ユーザーのためになりません。そのため、Googleは独自性のある、ユニークな価値を持つコンテンツを高く評価します。
記事を作成する際は、必ず「自分ならではの視点」「独自の経験談」「オリジナルの分析や考察」といった付加価値を盛り込むことを意識してください。あなたにしか書けない情報こそが、最大のSEO対策となります。
3. ユーザーを無視した専門用語の多用
専門性を示そうとするあまり、読者の知識レベルを無視して専門用語を多用することは、自己満足に過ぎません。読者が理解できない記事は、ただの「読みにくい記事」であり、すぐに離脱されてしまいます。
例えば、Webの初心者に向けた記事で、「このクエリに対しては、カノニカル設定でインデックスを最適化し…」といった説明をしても、ほとんどの人は理解できず、読むのをやめてしまうでしょう。
専門的な内容を、いかに平易な言葉で、身近な例えを使って分かりやすく伝えられるか。それこそが本当の専門性であり、読者からの信頼を得るための鍵となります。常に「この記事を読むのは、何も知らない初心者だ」という意識を持って、丁寧な言葉選びを心がけましょう。
AIライティングの全手順を動画で体系的に学ぶなら、私たちの『7日間無料講座』が最適です。詳細はこちらからご確認ください。
SEOライティングのやり方に関するよくある質問
最後に、SEOライティングのやり方に関して、初心者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。多くの人が疑問に思うポイントなので、ぜひ参考にしてください。
Q1. 文字数はどのくらい意識すればいいですか?
A. 結論として、「文字数を目標にする」のではなく、「読者の疑問を完全に解決するために必要な文字数を書く」という意識が重要です。
確かに、上位表示されている記事は文字数が多い傾向にあります。これは、読者の様々な疑問に答えようとした結果、網羅性が高まり、自然と文字数が増えたと考えるべきです。
まずは競合上位記事の平均文字数を参考にしつつも、単に文字数を稼ぐために無駄な内容を引き延ばすのはやめましょう。読者の検索意図を満たし、必要な情報をすべて盛り込むことを最優先に考えれば、おのずと最適な文字数になります。
Q2. AIにライティングを任せても大丈夫ですか?
A. AIを「優秀なアシスタント」として活用するのは非常に有効ですが、「丸投げ」は危険です。AIが生成した文章には、事実誤認や古い情報、独自性の欠如といった問題が含まれる可能性があるからです。
AIは、構成案の壁打ち相手としてアイデアを出してもらったり、文章のたたき台を作成してもらったりするのに非常に役立ちます。これにより、ライティングの作業効率を大幅に向上させることが可能です。
しかし、最終的な情報の正確性の確認(ファクトチェック)や、自らの経験に基づく独自性の追加、そして読者の心に響く表現への編集は、必ず人間の手で行う必要があります。AIと人間が協業することが、今後のコンテンツ制作の鍵となります。
Q3. 効果が出るまでどのくらいの期間がかかりますか?
A. 一概には言えませんが、一般的に3ヶ月から6ヶ月、場合によっては1年以上かかることもあります。SEOは、すぐに結果が出る魔法の杖ではありません。
効果が出るまでの期間は、サイトのドメインパワー(信頼性)、対策するキーワードの競合の強さ、コンテンツの品質と量など、様々な要因に左右されます。新しいサイトほど、Googleからの信頼を得るのに時間がかかる傾向があります。
大切なのは、短期的な結果に一喜一憂せず、長期的な視点でコツコツと質の高いコンテンツを作り続けることです。正しいやり方で継続すれば、必ず成果は現れます。焦らず、じっくりとサイトを育てていきましょう。
Q4. SEOライティングを学ぶのにおすすめの本はありますか?
A. Web上で最新情報を追うことが基本ですが、体系的な知識を学ぶなら書籍も有効です。定番の良書として以下の2冊がおすすめです。
1冊目は「沈黙のWebライティング —Webマーケッター ボーンの激闘—(松尾 茂起 著)」です。ストーリー形式で非常に読みやすく、SEOの基本的な考え方から実践的なライティングテクニックまでを網羅的に学べます。初心者の方が最初に読む一冊として最適です。
2冊目は「20歳の自分に受けさせたい文章講義(古賀 史健 著)」です。SEOに特化した本ではありませんが、「伝わる文章」の普遍的な型を学べます。ライターとしての基礎体力を鍛えたい方におすすめです。
AIライティングの全手順を動画で体系的に学ぶなら、私たちの『7日間無料講座』が最適です。詳細はこちらからご確認ください。
まとめ:正しいやり方を実践し、読者と検索エンジンに愛される記事を作ろう
本記事では、SEOライティングの基本的な考え方から、具体的な7つの手順、そして質を高める15のコツまで、網羅的に解説しました。SEOライティングとは、小手先のテクニックではなく、読者の悩みに真摯に向き合い、その答えを誰よりも分かりやすく提供しようとする「おもてなしの心」そのものです。
今回紹介した手順とコツを一つずつ実践すれば、初心者の方でも必ず成果を出すことができます。この記事をブックマークし、何度も見返しながら、読者と検索エンジンの両方から愛される、価値あるコンテンツを作成していきましょう。
AIライティングの全手順を動画で体系的に学ぶなら、私たちの『7日間無料講座』が最適です。詳細はこちらからご確認ください。